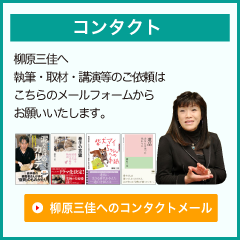「餅は最上の保存食」幕末、黒船の甲板で餅を焼いた日本人がいた
『開成を作った男、佐野鼎』を辿る旅(第56回)
2022.1.7(金)

正月休みもあっという間に過ぎてしまいました。でも、1月11日の「鏡開き」が終わるまではお餅を食べ、もうしばらく正月気分でいたいですね。
「全国餅工業協同組合」のサイトによると、“餅”は、奈良時代に編纂された『豊後国風土記』(713年)という書物の中に、白鳥の化身として登場するのだとか。以来、白い餅は縁起のよい白鳥のイメージと共に、「神秘な霊を宿すもの」と考えられ、ハレの日(お祝いのある特別な日)には餅をお供えし、食べる習慣が広がったそうです。
日本人と餅のかかわりには、長い歴史があるのですね。
万延元年遣米使節団、「黒船」の甲板で餅を焼く
一方、餅は「お供え」という縁起物のほか、長旅における「保存食」としても珍重されてきました。
本連載の主人公である「開成を作った男・佐野鼎(さのかなえ)」が幕末に記した『訪米日記』の中には、万延元年遣米使節(万延元年遣米使節について ――一般社団法人 万延元年遣米使節子孫の会 [1860kenbei-shisetsu.org])の随員として太平洋上を航海中、アメリカの軍艦・ポーハタン号の甲板上で「餅を焼いた」という興味深い記述があります。
ポーハタン号とは、1854年、ペリーが日本に来航したときの旗艦で、かの吉田松陰が密航を企てようとした艦船です。当時は「黒船」と呼ばれていましたが、1860年、その2年前に締結した日米修好通商条約の批准書をアメリカで正式に交わすため、日本人使節団(総勢77名)を江戸まで迎えに来て、1月18日にアメリカへ向けて出航していたのです。
![ポーハタン号[published by 東洋文化協會 (The Eastern Culture Association), Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で]](https://www.mika-y.com/upload/images/20220108101501.jpg)
佐野鼎が感心した元水夫の機転
さて、「餅」の話に戻りましょう。
まずは佐野鼎の日記から、大嵐の翌朝に書かれた一説をご紹介します。
<1860年1月27日>
【この朝、賄(まかない)方の者ひとり、甲斐々々しく衆に先立ちて起き出で、貯えたる餅を出し、火に焼きて衆人に一二片宛を与へたり。】
(この日の朝、調理担当の一人の男が早くから起きてきびきびと動き、貯えてあった餅を焼いて、使節団の面々に朝食として1~2個ずつ与えていた)
実は、日本人を乗せて航海中だったポーハタン号は、前夜から激しい暴風雨に遭遇し、大波にもまれて沈没寸前という被害に見舞われていました。
江戸を発って1週間余り、あまりに過酷な揺れに襲われた使節たちの多くは、ひどい船酔いに苦しみ、飲み食いはおろか、起き上がることすらできなかったようです。
それだけではありません、波にのまれた甲板は何もかもぐちゃぐちゃになり、かまどの傍に置いてあった大根の漬物樽、醤油樽、味噌樽、酢樽、飯櫃や薪の束なども海に流されてしまったというのです。このままでは揺れが収まっても、すぐに食事を用意することすらできないという状況でした。
ところが、賄い人のこの男は誰よりも早く起きて甲板に出ると、すぐに火を起こし、艦内に貯えてあった餅を取り出して黙々と焼き始めたというのです。
佐野鼎はこの男の機転の利いた行動を、感心しながら観察していました。
そして、日記はこう続きます。
【これにて飢えを凌ぎ、彼の者の働きを感じ、後彼の素性を聞きしに、元来大船乗の水師なりといふ。さもあるべし。常人にてはこの技は為し難かるべし。】
嵐の後の荒れ果てた甲板の上で餅を焼いていたのは、武蔵国(武州久良岐郡。現在の横浜市の一部)出身の久保寺半次郎という40代半ばの屈強な男でした。
おそらく、水夫としての経験をかわれ、使用人として今回の遣米使節団に随行したのでしょう。
緊急時におけるこの男の働きに感じ入った佐野鼎は、その後、この男の素性を尋ね、
『なるほど、さすがは海の経験を積んだ元水夫だ。こうした「技」は普通の人間には難しい・・・』
と記しています。日記の文面からは、半次郎に尊敬の念を抱いていることが読み取れます。
使節団が黒船に持ち込んだ食材のリスト
ちなみに、ポーハタン号には今回の航海のために、日本人用に銅製の大きな鍋が四つかけられるかまどが特別に備え付けられ、一回の火おこしで日本人77人分の白飯と汁物、煮物などが一度に煮炊きできるよう工夫されていたそうです。
このとき太平洋で遭遇した大嵐によって、甲板に置いてあった食材は流されてしまい、その後のことが心配されましたが、江戸を発つときに大量の食糧を積み込んでいたので、何とか事なきを得たようです。
賄い方として乗船した加藤素毛(そもう)という人物の日記には、長い航海に備えてポーハタン号に積み込んだ食材が細かく記してありました。
以下は、そのリストのほんの一部ですが、保存のきく米や豆、発酵食品、乾物類の確保は抜かりがありませんでした。
「御蔵米布袋入100俵、味噌10樽、醤油25樽、酒4樽、味醂1樽、酢1樽、胡麻油、白砂糖1包、沢庵漬20樽、梅干10樽、梅漬生姜1樽、鰹節2樽、卵700個入2箱、鯖干物5箱、蒟蒻2樽、若芽1籠、荒布2籠、昆布1籠、干大根3俵、切干大根1俵、黒豆1俵、塩松茸1樽、椎茸6斗、干貝1箱・・・」
そのほかにも、大根、人参、牛蒡、里芋、生姜などの新鮮な根菜類も相当量積み込まれていたようです。
それでも、緊急時には「餅」に勝る食材はなかった、ということでしょう。
大嵐で疲弊した使節団を元気づけた餅
大嵐の翌朝、ポーハタン号の甲板には、香ばしい焼き餅としょうゆの香りが漂ったに違いありません。アメリカ人水夫たちも、「何を焼いているんだ?」と覗きに来たかもしれません。
そして何より、船酔いで飲まず食わずだった多くの日本人が、この焼き餅のおかげで何とか飢えをしのぎ、生気を取り戻すことができたのです。
これは推測ですが、江戸時代、アメリカの軍艦の上で「餅を焼いた」初めての日本人は、おそらく、この「久保寺半次郎」ではないでしょうか。
歴史を変えるような出来事ではないかもしれません。でも、これも江戸幕府始まって以来、初の外交行事の中の一コマです。こうした些細なエピソードが、佐野鼎の『訪米日記』に綴られていることに、人間味のあるほのぼのした微笑ましさを感じます。
【連載】
(第11回)これが幕末のサムライが使ったパスポート第一号だ!
(第14回)151年前の冤罪事件、小栗上野介・終焉の地訪問記
(第15回)加賀藩の採用候補に挙がっていた佐野鼎と大村益次郎
(第16回)幕末の武士が灼熱のパナマで知った氷入り葡萄酒の味
(第17回)遣米使節団に随行、俳人・加藤素毛が現地で詠んだ句
(第19回)「勝海舟記念館」開館! 日記に残る佐野と勝の接点
(第20回)米国女性から苦情!? 咸臨丸が用意した即席野外風呂
(第21回)江戸時代の算学は過酷な自然災害との格闘で発達した
(第22回)「小判流出を止めよ」、幕府が遣米使節に下した密命
(第24回)幕末に水洗トイレ初体験!驚き綴ったサムライの日記
(第25回)天狗党に武士の情けをかけた佐野鼎とひとつの「謎」
(第29回)明治初期、中国経由の伝染病が起こしたパンデミック
(第30回)幕末の侍が経験した「病と隣り合わせ」の決死の船旅
(第35回)セントラル・パークの「野戦病院化」を予測した武士
(第36回)愛息に種痘を試し、感染症から藩民救った幕末の医師
(第37回)感染症が猛威振るったハワイで患者に人生捧げた神父
(第38回)伝染病対策の原点、明治初期の「コレラ感染届出書」
(第39回)幕末の武士が米国で目撃した「空を飛ぶ船」の報告記
(第40回)幕末の裏面史で活躍、名も無き漂流民「音吉」の生涯
(第42回)ツナミの語源は津波、ならタイフーンの語源は台風?
(第43回)幕末のベストセラー『旅行用心集』、その衝撃の中身
(第44回)幕末、米大統領に会い初めて「選挙」を知った侍たち
(第45回)「鉄道の日」に紐解く、幕末に鉄道体験した侍の日記
(第48回)「はやぶさ2」の快挙に思う、幕末に訪米した侍の志
(第49回)江戸で流行のコレラから民を守ったヤマサ醤油七代目
(第51回)今年も東大合格首位の開成、富士市と協定結んだ理由
(第52回)幕末に初めて蛇口をひねった日本人、驚きつつも記した冷静な分析
(第53回)大河『青天を衝け』が描き切れなかった「天狗党」征伐の悲劇